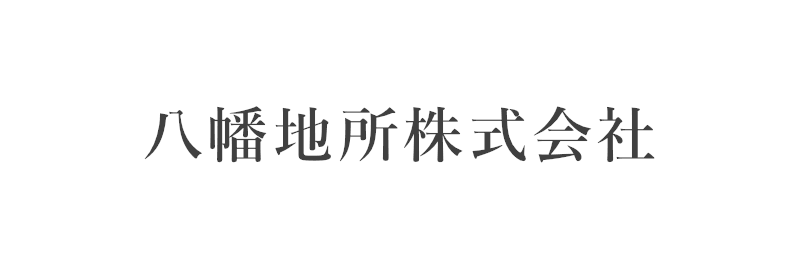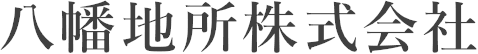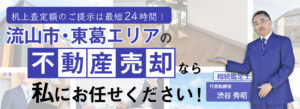共有名義の不動産を売却したいと考えている方の中には、「自分一人の判断で売却できるのか?」「他の共有者と意見が合わないときはどうなるのか?」など、さまざまな疑問や不安を抱えている方が多いのではないでしょうか。
実際、共有名義の不動産売却は、通常の単独名義の売却に比べて複雑な要素が多く、手続きや合意形成に注意が必要です。本記事では、「不動産売却 共有名義」と検索された方に向けて、基礎知識から実際の手続き、トラブルの対処法、名義の解消方法までをわかりやすく丁寧に解説します。
初めて不動産売却を検討する方でも安心して読み進められるように、専門用語も平易な言葉でご説明します。
1. 共有名義の不動産とは?

共有名義の不動産とは、一つの物件を複数人で所有しており、それぞれが「持分」と呼ばれる割合に応じた権利を持っている状態です。夫婦で住宅を購入した場合や、親の不動産を兄弟姉妹で相続した場合などが代表的です。各共有者は不動産の使用や収益を分け合う一方、売却や担保設定などの重要な判断には全員の同意が必要になります。単独名義とは異なり、共有名義は意思決定の複雑さや手続きの煩雑さが伴う点に注意が必要です。
1-1 共有名義とは何か?単独名義との違い
不動産の名義には「単独名義」と「共有名義」があります。単独名義とは、1人がその不動産の所有権を100%持っている状態のことです。この場合、売却や賃貸、担保設定など、すべての手続きはその名義人1人の意思決定で完結します。
一方、共有名義とは、1つの不動産を複数人で共同所有している状態を指します。各人が持分(例えば夫婦で半分ずつなら50%ずつ)を持ち、法律上はその割合に応じた権利を有します。よくある共有名義の例としては、以下のようなケースが挙げられます。
夫婦で住宅ローンを組んで購入した場合
親から複数の兄弟姉妹に相続された不動産
離婚後も不動産の名義を共有のままにしている場合
1-2 不動産売却時に共有名義が及ぼす影響
不動産を売却するには、その不動産の「所有者全員の同意」が必要です。共有名義の場合、名義人のうち一人でも売却に反対していれば、その不動産を売ることはできません。これは民法で定められており、法的に強いルールです。
また、売却の契約書にも共有者全員の署名・押印が必要になります。さらに、共有者が高齢だったり遠方に住んでいたりすると、印鑑証明書の取得や契約書のやり取りにも時間がかかることがあります。結果として、単独名義の不動産に比べて、売却の手続きが煩雑になり、時間と労力を要する傾向があります。
2. 共有名義の不動産売却に必要な同意

共有名義の不動産を売却する場合、名義を持つ全員の明確な同意が不可欠です。たとえ1%の持分しか持たない共有者がいても、その人が反対すれば売却は成立しません。売買契約や登記手続きにも、共有者全員の署名と押印、印鑑証明書が必要になります。また、意思確認や書類準備に時間がかかることも多く、スムーズな売却を実現するには、事前に合意形成を行い、関係者との信頼関係を築いておくことが重要です。
2-1 売却には全員の合意が必要な理由
民法第251条では「共有物の管理および変更には共有者全員の同意が必要」と明記されています。不動産の売却は“管理”ではなく“処分”にあたり、これは全員の「明示的な同意」がなければ実行できません。
例えば、3人で共有している土地を売る場合、その3人すべてが「売ること」に納得し、署名・押印する必要があります。仮に1人でも「反対」「考え中」といった曖昧な態度であっても、契約は成立しません。
2-2 合意が得られない場合の対応方法
全員の同意が得られない場合は、以下のような対処法が検討されます。
① 持分の売却
共有者が自身の持分のみを第三者に売却することは法的に可能です。ただし、市場価値は大幅に下がり、買い手も限定されます。買主は「他人と共有する不動産」を持つことになり、利用制限が多いためです。
② 共有物分割請求訴訟
話し合いで解決できない場合、家庭裁判所や地方裁判所に「共有物分割請求訴訟」を起こすことができます。判決により、不動産の分割や売却、換価分割(売却して代金を分配)が行われます。
③ 家庭裁判所での調停
裁判の前に、家庭裁判所での調停を利用することも可能です。調停委員を介して話し合いが進められ、合意形成を目指します。比較的穏便に解決できる手段として有効です。
3. 共有名義不動産売却の進め方

共有名義の不動産売却を円滑に進めるには、全共有者の合意を得たうえで、段取りよく準備を進める必要があります。まずは登記簿謄本で持分割合を確認し、必要書類を揃えましょう。その後、共有者全員の名義で不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を開始します。買主が決まった後は、契約締結・決済・引き渡しの各段階で全員の参加・協力が不可欠です。スケジュール調整や情報共有も、成功のカギとなります。
3-1 売却前にやるべき準備とは?
不動産売却を進めるには、まず以下のステップを踏みましょう。
全共有者の意志確認:売却に対して全員が同意しているかを確認する。
権利関係の確認:登記簿謄本で名義人と持分割合を明確にする。
必要書類の準備:印鑑証明書、本人確認書類、登記識別情報、権利証など。
また、共有者同士の信頼関係が薄い場合には、司法書士や弁護士などの専門家に立ち会ってもらうとトラブルを避けやすくなります。
3-2 売却手続きの流れと実務ポイント
不動産会社への相談と媒介契約の締結
共有者全員で不動産会社を選び、媒介契約を結びます。
販売活動と買主の募集
買主候補が現れた段階で、共有者全員と条件のすり合わせを行います。
売買契約締結
全員が売買契約書に署名・押印し、印鑑証明書を提出します。
決済・引き渡し
代金の受領後に登記手続きを行い、買主へ引き渡します。
この一連の流れで重要なのは「共有者全員が同時に動けるかどうか」です。スケジュールを共有し、誰か一人でも不在や遅れが生じないよう、事前にしっかり調整しておくことがカギです。
4. 相続や離婚で共有になった場合の注意点

相続や離婚をきっかけに共有名義となった不動産は、利害や感情が絡みやすく、売却時の合意形成が難航するケースが多いです。相続では遺産分割協議を通じて名義と持分を整理する必要があり、協議書がなければ名義変更も進みません。離婚の場合は、財産分与の合意が取れていないと、不動産の扱いがあいまいになりトラブルを招く恐れがあります。事前に法的手続きと役割分担を明確にしておくことが重要です。
4-1 相続で共有名義になった不動産の売却対応
親が所有していた不動産を子どもたちで相続した場合、自動的に共有名義となることが多いです。売却を進めるには、まず「遺産分割協議」を行い、誰がどのような割合で不動産を相続するのかを決めます。その結果をまとめた「遺産分割協議書」がないと、名義変更すらできません。
また、相続税の申告や名義変更には期限もあります。売却を考えているなら、相続発生後できるだけ早く専門家に相談し、段取りを整えましょう。
4-2 離婚で共有名義となった場合の解決策
夫婦で住宅を購入し、離婚後も名義が共有のままになっている場合、扱いが難しくなります。離婚時の財産分与で「家は売却して清算」と合意できていればよいのですが、感情的な対立が絡むと合意形成が困難です。この場合、以下のような解決方法が考えられます。
どちらかが相手の持分を買い取って単独名義にする
不動産を売却し、利益を分ける
調停を利用し合意形成を図る
住宅ローンが残っている場合は、債務者の変更も必要になり、金融機関との調整も不可欠になります。
5. 共有名義を解消してから売却する方法

共有名義のままでは意思統一が難しく、売却に時間がかかることもあるため、単独名義に変更してから売却するという方法も有効です。具体的には、他の共有者の持分を買い取ったり譲渡してもらったりして、自分一人の名義にすることで、売却手続きをスムーズに進められます。ただし、税務面での注意点や、贈与とみなされるリスクもあるため、譲渡価格は時価を基準とし、専門家のサポートを受けることが望ましいです。
5-1 持分の売却・譲渡で単独名義に変更する方法
共有名義のままでは売却が難しいと感じる場合は、持分を買い取ることで単独名義に変更する方法もあります。例えば、自分が70%の持分を持ち、残りの30%を兄弟が所有している場合、その兄弟から持分を買い取れば、全体を自分の名義にできます。これにより、売却手続きが自分一人で完結できるようになります。
5-2 共有名義の解消にかかるコストと注意点
持分の買い取りには当然ながら費用がかかります。時価での譲渡が原則となり、税務上も注意が必要です。特に親族間での譲渡の場合、「時価より安すぎる価格」で取引すると「贈与」とみなされ、贈与税が課せられることもあります。また、名義変更には以下の費用が発生します。
登録免許税
司法書士への報酬
不動産取得税(条件により免除)
これらの費用と手間を事前に確認し、経済的な負担も含めて対応を検討することが大切です。
6. まとめ

共有名義の不動産売却には、法的・実務的な複雑さが伴います。特に「全員の合意」「書類準備」「スケジュール調整」など、関係者の協力が欠かせません。
スムーズな売却を実現するために、以下の点を意識しましょう:
初期段階での意思確認と合意形成
売却の前に名義を整理・解消する選択肢の検討
専門家(不動産会社・司法書士・弁護士)との連携
不安を抱えながら進めるのではなく、信頼できるプロとともに段取りよく進めることで、不要なトラブルや損失を避けることができます。共有名義の不動産売却でお困りの際は、ぜひ早めに相談窓口へアクセスしてみてください。